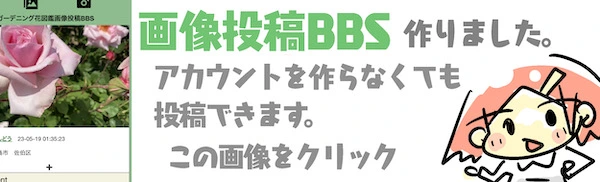シラキの育て方
TOP > トウダイグサ科 最終更新【】シラキ

| 科名 | トウダイグサ科 |
| 属名 | シラキ属 |
| 学名 | Sapium japonicum |
| 別名 | 白木・白乳木 |
| 水やり | 水控え目 |
| 場所 | 外の日なた |
| 難易度 | 中級者向け |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 開花 | ||||||||||||
| 植え | ||||||||||||
| 肥料 |
スポンサーリンク
シラキとは?
シラキはトウダイグサ科の落葉高木。本州から沖縄まで自生する。5月から7月に開花。雌雄同株で雌雄異花で、一本のシラキに雄花と雌花がつく。花びらのない地味な花です。10月11月に実をつける。また寒さに当たると紅葉する。紅葉はシラキの魅力。春になると赤い新芽をつける。赤い新芽が枝先から垂れ下がるけど、病気じゃないです。シラキは性質が頑健で、育てやすい。環境はあまり選ばず、環境に慣れれば問題なく育つ。成長は早く、小さくまとまるように剪定する必要がある(大きくなってもいいならそれでいいけど)。
地味な木だけど、「自然の山」「自然の庭」って感じがして、シンボルツリーとして植えられることも多くなった。ナンキンハゼに近く、繁殖力が強い。放置していると周囲に生えてくるので、不要なら引っこ抜く覚悟を持つべき。
樹高7m前後
水やり
水やりは普通。庭植えの場合は一旦根付いてしまえば自然に降る雨だけでほぼ十分。日照りの時に水をやる程度です。
鉢植えの場合は土が乾いたら水をやります。水をやるときは鉢底から水がしみ出すくらいにしっかりとやります。土が濡れている間は水やりをしないでください。根腐れを起こします。水をやったら、次には土が乾くまで水をやらない…メリハリのある水やりをしましょう。受け皿の水は捨ててください。
参考:水やり三年…水やりは難しい。(初心者向き)
肥料
生育が悪いなら2月に寒肥として化成肥料か油粕+腐葉土か油粕+堆肥を周囲に穴を掘って(根に当たらないような位置に掘って)追加する。それとは別に6月に肥料をやるといいです。庭植えにしたら、肥料はほとんど不要。葉色が悪く、肥料不足っぽいなら肥料をやる程度。鉢植えにした場合は2月と6月に肥料を鉢のフチに置くといいです。
植え付け・植えかえ
時期・頻度
10月以降、落葉時期に植え付けをします。寒冷地で植える場合は4月以降にします。鉢植えは2年に一回植え替えをします。用土
土質はあまり選ばない。常識的な用土であれば問題なし。鉢植えにするならば一般的な花と野菜の培養土で植えるか自作する場合は赤玉土小粒6腐葉土4を混ぜたものを使う。庭植えにする場合は、庭土に腐葉土か堆肥を2割か3割ほど混ぜてから植えます。シラキは多少ジメジメした場所に群生していることが多いのですが、普通の土でも十分に育ちます。
鉢植えの植え付け・植え替え
鉢植えの場合は、根鉢(ポット)より一回り大きな鉢を用意し、苗の土を崩さずに植え付けます。植え替えのときも土を崩さず根をいじらないで植え替えましょう。鉢底の穴をアミで塞いで土が出ないようにしてから軽石を2センチから3センチほど入れて、鉢底石(軽石)の上に土を入れ、株を入れて、隙間に土を入れていき、最後に水をやります。鉢底から水が出るまで水をやってください。
庭植え(地植え)の手順は?
庭植えの場合は、根鉢の二倍か三倍の深さと大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割混ぜて用土とします。穴に半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。グラグラするなら支柱をしましょう。管理場所・日当たり
日当たりに植えましょう。日当たりでないと秋の紅葉が鈍くなるので必ず日当たりのいいところに植えるようにする。多少の半日陰でも枯れるわけじゃないですから、半日陰でもいいです。寒さに強く、北海道南部でも戸外で生育します。
剪定
剪定時期は2月から4月の落葉していて、もうすぐ新芽が出るころ。自然な樹形が魅力なので、強い剪定はしない。もしくは全然剪定しない。強い剪定をすると枯れ混むことがある。ノコギリを使わないといけないくらい太い枝を切るときは癒合剤を塗る方が良い。
一般的に庭植えにしていると大きくならない(庭は横にも下にも根を張るスペースがないため)ことが多いが、根を張るスペースがあって順調に行くと5m以上とか下手すると10mとかになる。しかも結構生育が早い。大きくなると厄介なので大きくなりそうなら、剪定して小さくまとめるようにする。
小さくまとめるには、幹のてっぺんを切ってしまう。これでしばらくは上に伸びなくなる。ただし、しばらくすると上に伸びる枝が出てくるので、それを切るようにする。詳細は芯止めを参考にしてください。
あなたの年齢的(か肉体的)に管理が厳しいと思ったら、業者に頼んで引っこ抜いてもらうようにしましょう。
病害虫
基本的に病害虫が発生しても大ごとにはならない。イラガ(ただし、さほど大量には発生しない)。
特徴・由来・伝承
樹皮が白いというか灰色であることが白木の由来とされるが、枝を切ると、白い乳液状の樹液が出るので、名前の由来はそちらの可能性もある。冬は落葉し、春には芽吹く。種子には脂が多く、燃料にもなるらしい。種子はトラ柄。スポンサーリンク